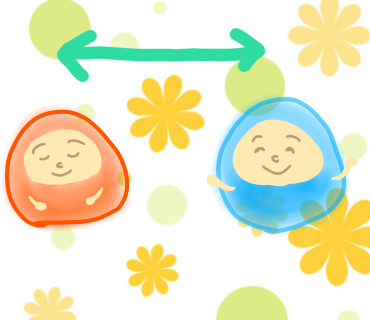
もらいうつを防ぐために大事になることは「相手との適切な距離を保つこと」。
私の体験を踏まえつつ、イヤな気分をパッと手放す「自分思考」のすすめ:他人にも感情にも振り回されない方法からの引用を参考に、考えていきたいと思います。
広告- - - - - - - - - -
相手との適切な距離を保つのは意外と難しい
私自身もうつ(と思われる状態)の経験があるので、うつ状態にある人と接すると「気持ちがわかるからこそ、寄り添いたい」と思います。
そして、自分が辛かったときのことを思い出し「当時の私は、周りの人にこんなことをしてほしかったな」「ありのままの私を認めてほしかったな」と思い出すんですね。
だから「じゃあ、こんな言葉をかけよう」とか「こういう態度で接しよう」とか思うんですよ。
でも、相手がそれを望んでいるかどうかは……わからないのですよね。
「うつのときの辛い気持ち」自体は想像できても、「具体的にどうしてほしいか」は違うかもしれませんから。
また、「うつ」と一言で言っても、症状はそれぞれ異なりますし、相手の現在の状態に合わせた対応ができるかといったら、それも素人には難しい問題です。
つまり、「私はうつのときはこうしてほしかった」ということも、決して相手にとっての処方箋とは限らないんですよね。むしろ悪化させる可能性さえはらんでいる。
にも関わらず!!!
こちらの「寄り添いたい」気持ちが、相手に全然響いていないように見えると、なんだか焦りのようなものを感じてしまうんです。
すると余計に「実はこういう気持ちだったのでは?」「〇〇と言ってあげれば楽になったのかな」「次はこうしよう」とか、相手のことで頭がいっぱいになってしまいます。
そして、相手の気持ちを読もうとするのを長く続けていると、「私には人を元気づける力がない」という無力感に襲われるようになったり、最終的には「(こんなに気を遣っているのにそれに応えない相手が)嫌い」となってしまうこともありえる。
相手からしたら超迷惑ですよね(汗)
乱暴に言い換えれば「私がこんなに気を遣ってやっているのだからさっさと元気になれ」と押し付けられていると感じるかもしれません。
そう感じさせてしまったのだとしたら、ちっとも「相手のありのまま」を認められていないことになります。一番やってはいけないやつです。
「相手のありのままを認める」ということが、概念としては理解できていても、実際の行動として私はまだおそらくできていないのだと、この記事を書きながら実感しました(反省……)。
悩んでいる本人ですら、ほんとうの気持ちがわからないことも多い
自分のことを人はわかってくれません。それなら自分も、人のことなんかわかるわけがありません。専門家でもわからないことがあるのです。本人にしかわからないことがあるし、本人ですらわからないことがあるのです。そこをはき違えると、相手のことが嫌いになってしまいます。
玉川真理『イヤな気分をパッと手放す「自分思考」のすすめ』誠文堂信光社(2017)P.187
たしかに、悩んでいる当の本人も、わかっているつもりで実はわかっていないこともあるんですよね。
私もそうだったんです。
若い頃の私は「周囲に気を遣っているのにも関わらず、なぜ私は批判ばかりされるのだろう」と不満に思っていました。
当時は気づいていなかったのですが、心の底から求めていたのが「まるごと受け止めてもらう」だったんですよね。別の言葉で言い換えると「親の代わりをしてくれる人(=自分をまるごと受け止めてくれる人)」を探し求めていたんです。
なので、「自分が希望する形で肯定してもらう」以外はほぼ「批判された」と大げさに捉えてしまっていたんですよね。
具体的なエピソードでいうと、基本的にいつも不満をグチグチ言ってしまっていた私に対し、「こうしたら楽だよ」と言ってくれた知人がいたんです。
それを聞いた私は「(気持ちの持ち方次第で解決するんだから)グチグチ言うな。聞かされるほうも迷惑!」って言いたいのだろう、と勝手に傷ついてしまいました。
でも、何年も経ってから「こうしたら楽だよ」が本当にその通りだとわかり、その知人は私を否定するつもりではなく、単純に「この方法いいよ」とおすすめしてくれたのかもしれない、と思い直しました。
でも、あのときの私の心には、入らなかったんですね。
とにかく「全部いいよ」と言ってもらわないと気が済まなかったんです。
子供の頃から親に否定され続けた結果、否定アレルギーみたいになってしまっていて、「全肯定」以外は、受け付けられなくなってしまっていたんです。
それなのに、「否定アレルギーである」という認識が自分では持てなかったんですよね。
アレルギー物質を自ら摂取しにいって、「うわーぎゃー苦しいー」と騒いでいたんです……。
まあ、仮に、「否定アレルギー」を認識できたとしても「全肯定以外NGなんて、わがまますぎる」と抑圧してしまったと思いますが。
つまり、本人さえも抑圧している「ほんとうの願望」がわからないと、本人も、周囲も根本的には対処できないんだろうな、と思うのです。
だから、うつで苦しんでいるひとに楽になってもらいたい、と何らかの言葉をかけたとしても、「本人が本当にかけてもらいたい言葉」でないと、逆に傷つけてしまう可能性のほうが高いのかもしれないな、と思います。
広告- - - - - - - - - -
まとめ
・悩んでいる本人ですら「本当にかけてもらいたい言葉」「本当にしてもらいたいこと」が明確でないことも多い
・「よかれ」が干渉になってしまう懸念もある
・だから双方とも負担にならない程度の「距離」が必要
悩んでいる人を助けるというのはおそらく想像以上に難しくて、「助ける」というよりはおそらく、一緒に道を探していくというか、「本人の思考整理が進むように見守る」というのが一つの解になるのだろうと思います。
それも難しいんですよね……。
私自身が「ああしろこうしろ」と言われてきた派なので、つい人にも言ってしまう(嫌だとわかっているのに)。。。
参考文献
イヤな気分をパッと手放す「自分思考」のすすめ: 他人にも感情にも振り回されない方法