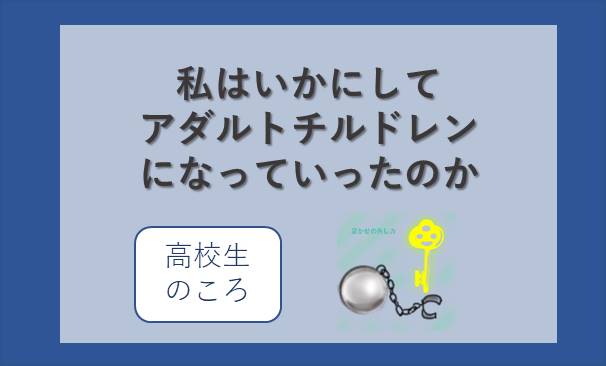
過去の痛みを成仏させるため、自分の育った家庭を改めて客観視する作業をしています。(関連記事一覧はこちら>>>【もくじ】いかにして私はアダルトチルドレンになっていったのか【体験談】)。
進学校に入ったはいいものの、勉強しようとしても、問題文が頭に入ってこない勉強版「イップス」のような状態になっていました。
それは受験直前になっても続き、当然、大学受験の結果はほぼ全敗。
よい結果を出していく同級生たちがうらやましくて、自分自身がふがいなくてたまりませんでした。
広告- - - - - - - - - -
大学受験、ほぼ全敗
頭では「勉強しなくちゃ」、でも心では「もう勉強したくない」が常に綱引きの状態。
机に座って参考書を開いてはいるものの、実際は何もできませんでした。
本当に何もしないならまだしも「なんで私は集中できないんだ、周りのみんなはできるのに」「なんてふがいないんだ」「なんて私はダメなんだ」などなど、自分を責めることばかりやっていました。
「なんてダメなんだ」と思っている間に、一個でも何か覚えればいいのに、文章が、数式が、図が、全く頭に入ってこないのです。
そのくせ、プライドだけはねじ曲がっているので、現実の成績を見ることもできませんでした。
「うちの高校から進学するならこれ以上じゃないと恥ずかしい」みたいな、変なこだわりがあったのです。
結果は当然、ほぼ全敗(センター試験利用で一校くらい受かったような気もするのですが、辛い記憶すぎて全然覚えてない)。
そこまで事実をつきつけられてもなお、実際の実力というものを、私は見つめることができませんでした。
クラスメイトたちがうらやましい/私は恥ずかしい存在
ヘトヘトになりながら、ようやく希望の大学に受かった人もいましたが。
その一方で、塾にも行かず、受験期でもマイペースに淡々と暮らし、軽々と合格した子もいました。
元々の頭のよしあしもあるかもしれませんが、そういう子は、普段の授業を大切にしていたように思います。
一回一回、納得してから授業を終えているというか。
私が、できもしない問題集にあれこれ手を出していた一方、彼女たちは学校指定の問題集をただ粛々と、繰り返しこなしていました。
まさに、地に足がついているというか。
その様子が、すごくまぶしかったのです。
足元がぐらぐらで、いつも「勉強ができなくて恥ずかしい」と思いながら、「でも劣等感をあまり見せないようにしなくちゃ」と変な力の入れ方をしていた私。
体の力を抜いたら浮き上がることができるのに、「水泳選手みたいにカッコよく泳がなくちゃ」と手足をバタバタさせてしまって、余計に事態が悪化しているような。
間違った方向に進んでいることに、うっすらと気づいているのに、向き合えなかったのです。
「いや、私だって、そのうちなんとかなる」と。
残念ですが、そう思っているときはならないんですよね。
自分で自分の現実を認めない限り、そこから抜けだすことは難しいのです。
道に迷ったときに、現在地がどこかわからないと、地図を見ても目的地がどっちの方向かすらわからないのと同じなのです。
広告- - - - - - - - - -
【この体験から学ぶこと】
諦めずにいろんな人の意見を聞いてみればよかった
当時の私がすべきだったことは、
・現在地を把握する(勉強したくないと思っていること、勉強が手につかないこと、実際に成績が良くないことなど)
・それを踏まえて今後どうするか考え直す
ということでした。
でも、自分の現実を正しく見るのって、安全地帯にいないとできないのですよね。
ライオンに追いかけられながら、立ち止まって「あ、靴に穴あいてる」なんてやっていたら、食われてしまうのと同じ。
家庭が危険地帯だと、現実を見つめている間に足元を救われて、よけい厄介な状況に陥ったりします。
だから、あのときの私にとっては、目を逸らすほかなかったのかもしれません。
唯一可能だったことがあるとすれば、「とにかくいろんな大人に相談してみればよかった」ということ(※親や親戚は除く)。
あのときの私は、「ほかの大人たちも、うちの親と大して変わらない」と思い込んでいました。
「相談してもどうせみんな似たようなことしか言わないんだろう」と。
それはある程度は当たっていたかもしれません。
今ほど多様性のある時代でもありませんでしたから。
10人相談したら8~9人くらいは当たり障りのないことしか言ってくれなかったでしょう。
でも、一人くらいは同じ道を苦しみながら通ってきた人がいたかもしれません。
いなかったとしても、10人に相談するうちに、少なくとも、自分の中のごちゃごちゃが整理されていって、気持ちがクリアになったかもしれない、と思います。
本当の答えは、実は、自分が知っているので、他の人からもらう必要はないのだと最近は思うようになりました。
だからこそ、自分の気持ちや状況を正確に自覚することのほうが大事なのだと今は考えます。
最近はインターネットがありますし、いくらでも相談先があります。
ラジオの相談コーナーに投稿したり、お寺のお坊さんに相談したり、カウンセラーに相談したり、いくらでも手段があります。
その「答え」に従えというわけではありません。
しっくりくる答えがすぐに見つからなくても、うんうん唸りながら探していくうちに方向性が決まっていく、これ自体に意味があるのではないかと思うのです。
なかには傷ついてしまう意見もあるでしょうし、毒親育ち特有の「アドバイスされたらそれに従わないといけないと思ってしまう」という呪いが邪魔をしてくるので、必ずしも良い結果につながるとも限らないのですが(10代の私にはやっぱりできなかっただろうと思う)。
勉強に限らず、八方ふさがりのときこそ、たくさんの人に相談して風穴を開けるのがいいのかなと、今改めて思います。
ほかの記事
機能不全家族体験談 一覧>>>私はいかにしてアダルトチルドレンになっていったのか 【体験談】
広告- - - - - - - - - -
